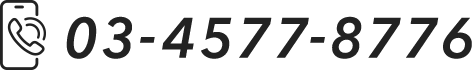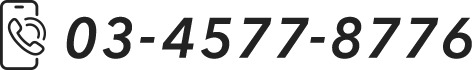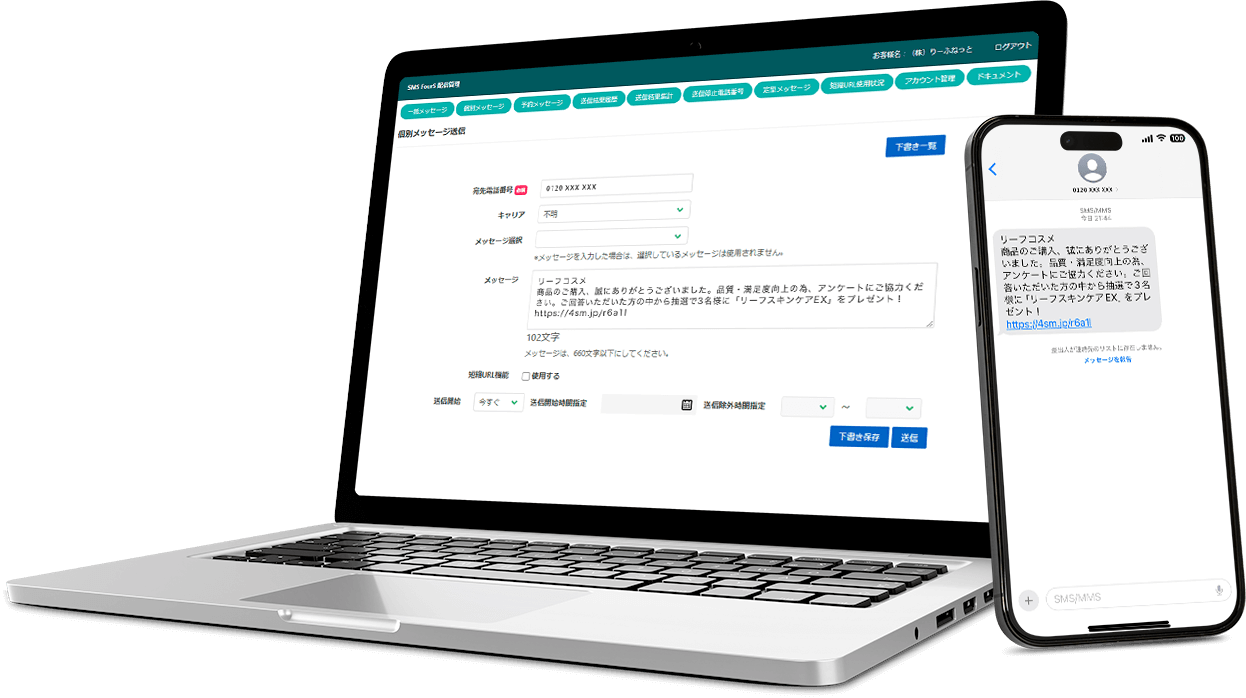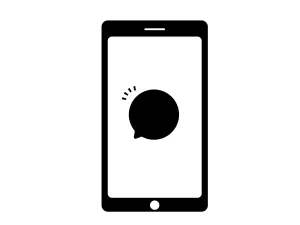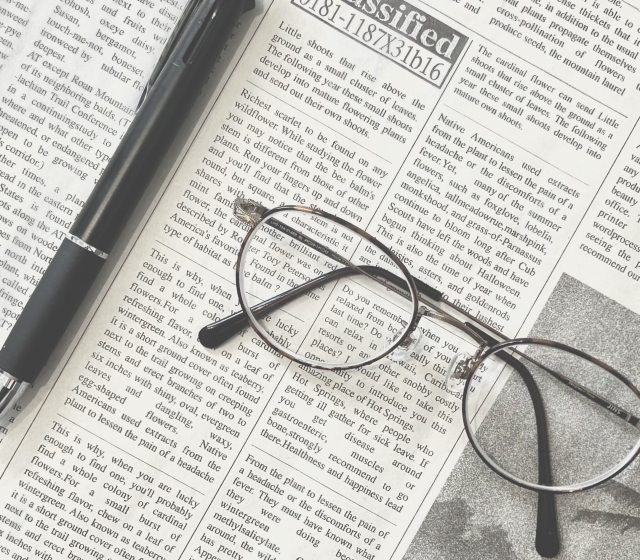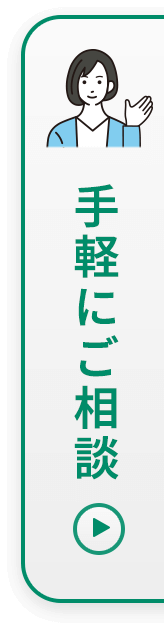「うちは多要素認証(MFA)を導入しているから、セキュリティは万全だ」
多くの企業やシステム管理者がそう考えているかもしれません。しかし、その「常識」を根本から覆す、極めて巧妙なサイバー攻撃が「リアルタイムフィッシング」です。この攻撃は、従来「安全の切り札」とされてきたSMS認証や認証アプリ(TOTP)すらも無力化し、企業の機密情報や金融資産を深刻な危険に晒します。
本記事では、この「リアルタイムフィッシング」とは何か、なぜ従来のMFAが突破されてしまうのか、その恐ろしい攻撃メカニズム、そして企業が今すぐ講じるべき本質的な防御策について、専門的な観点から徹底的に解説します。
リアルタイムフィッシングとは?
リアルタイムフィッシングとは、攻撃者が被害者と正規のWebサービス(例:Microsoft 365, Google Workspace, オンラインバンキング)との間に「中間者」として介在し、認証情報をリアルタイムで盗み取る攻撃手法です。
これは「AiTM(Adversary-in-the-Middle:中間者攻撃)」の一種であり、従来のフィッシング攻撃とは危険性が根本的に異なります。
従来のフィッシングは、IDとパスワードという「静的な情報」を盗むことが目的でした。 一方、リアルタイムフィッシングは、IDとパスワードに加えて、「MFA認証コード」や認証成功後に発行される「セッションクッキー」までもリアルタイムで窃取し、正規のセッション(ログイン状態)そのものを乗っ取ることが目的です。
なぜ「MFA認証コード」が突破されるのか? その巧妙な攻撃メカニズム
多くが信頼を置くMFA認証コードが、なぜこの攻撃の前では無力なのでしょうか。そのステップを詳細に解説します。
誘導(フィッシングメール・SMS)
攻撃の起点(入口)は、従来のフィッシングと変わりません。 「Microsoft 365のセキュリティ警告」「Google Workspaceのアカウントがロックされました」「社内システムへの再ログインが必要です」といった、緊急性を煽る偽のメールやSMS(スミッシング)が従業員に送信されます。
偽装サイト(リバースプロキシ)へのアクセス
被害者が文中のリンクをクリックすると、本物と見分けがつかないほど精巧に作られた偽のログインページに誘導されます。
ここが最大のポイントですが、この偽サイトは単なる「張りぼて」ではありません。攻撃者が用意した「リバースプロキシサーバー」として機能しています。被害者がこの偽サイトで行うすべての操作は、瞬時に正規のログインページへ転送(中継)されます。
認証情報の中継(IDとパスワード)
被害者は偽サイトとは気づかず、自身のID(メールアドレス)とパスワードを入力します。 攻撃者のサーバーは、その情報をリアルタイムで受け取り、即座に正規のサイトへ送信します。
MFA認証コード要求の横取り
正規のサイトは、IDとパスワードが正しいことを確認すると、当然ながら「MFA認証コード」を要求します。例えば、「SMSに送信された6桁のコードを入力してください」「認証アプリの番号を入力してください」といった画面を返します。
攻撃者のサーバーは、このMFA認証コード要求画面をそのまま受け取り、被害者のブラウザに表示(中継)します。
MFA認証コードの窃取と中継
被害者は、正規のプロセスだと信じ込み、自身のスマートフォンに届いたSMSコードや、認証アプリに表示されたワンタイムパスワード(TOTP)を、偽サイトの画面に入力します。
攻撃者のサーバーは、その認証コードをリアルタイムで受け取り、即座に正規のサイトへ送信します。
セッションハイジャックの完了
正規のサイトは、正しいID、正しいパスワード、そして正しいMFA認証コードを受け取ったため、これを「正規のログイン」として認証を許可します。
ここで、攻撃者は2つのものを同時に手に入れます。
- 正規のログイン権限
- 認証が成功したことを示す「セッションクッキー」
攻撃者はこのセッションクッキーを自身のブラウザにコピーすることで、MFA認証コードのプロセスを再度行うことなく、被害者になりすまして正規のサービス(社内システム、メール、クラウドストレージ)に自由にアクセスできるようになります。これが「セッションハイジャック」です。
被害者側は、MFA認証コードを入力した後に「エラーが発生しました」と表示されたり、正規のポータルサイトにリダイレクトされたりするため、攻撃が成功したことに気づきにくいのが特徴です。
従来のフィッシング対策が通用しない理由
リアルタイムフィッシングの脅威は、これまでのセキュリティ教育や対策が前提としていた「常識」を覆す点にあります。
1. SMS認証・認証アプリ(TOTP)の限界
SMSやGoogle Authenticatorなどの認証アプリ(TOTP)は、「そのコードを知っていること」を認証の要素としています。しかし、システム側は「誰がそのコードを入力しているのか」までは判別できません。

リアルタイムフィッシングは、正規の利用者本人にコードを入力させ、それを横取りして中継するだけです。そのため、MFAの仕組み自体は機能していても、攻撃者を防ぐ壁としては機能しないのです。
2. 従業員教育の限界
「URLを必ず確認しましょう」というセキュリティ教育は重要です。しかし、攻撃者も進化しています。
- タイポスクワッティング:
microsoft.comをmicros**0**ft.comにするなど。 - ホモグラフ攻撃:見た目が同じ別の文字(例:キリル文字の「а」)を使う。
- 正規ドメインの悪用:
login.microsoft.security-update.comのように、一見正当に見えるサブドメインを作成する。
多忙な業務中、これらの微細な違いをすべての従業員が常に見抜くことは、現実的に不可能です。
リアルタイムフィッシング被害の兆候と対処法
万が一、攻撃を受けた、あるいはその疑いがある場合、以下の兆候に注意し、即座に対処する必要があります。
被害の兆候
- 自身が操作していないタイミングで「(別端末・別地域から)MFA認証が成功しました」という通知が届く。
- 利用中のMicrosoft 365やGoogle Workspaceから、突然強制的にログアウトさせられる。
- 送信した覚えのないメールが送信済みトレイにある、あるいはファイルが削除・変更されている。
- セキュリティログに、見慣れないIPアドレスや地域からの「認証成功」の履歴が残っている。
対処法
- システム管理者への即時報告:最も重要です。個人の判断で対処しようとせず、直ちにIT部門またはセキュリティ担当部署(CSIRT)に連絡します。
- パスワードの即時変更:ログイン可能であれば、即座にパスワードを変更します。
- 全セッションの強制終了:システムの管理者は、該当アカウントの「すべてのアクティブなセッション」を強制的に切断(サインアウト)する必要があります。これにより、攻撃者が盗んだセッションクッキーが無効化されます。
- ログの保全と調査:管理者は、侵害が疑われる時間帯のアクセスログ、操作ログを保全し、被害範囲(どの情報にアクセスされたか)を特定します。
リアルタイムフィッシングを防ぐための「本質的な」対策
従来の対策が通用しない以上、企業は防御戦略を根本から見直す必要があります。
【最重要】フィッシング耐性MFA(FIDO2/Passkey)への移行
この攻撃に対する最も強力かつ根本的な解決策は、「フィッシング耐性」を持つMFAへ移行することです。具体的には「FIDO2(WebAuthn)」規格に基づいた認証を指します。
- 代表的な手段:
- セキュリティキー(YubiKey, Google Titan Keyなど)
- 生体認証(Windows Hello, Face ID, Touch ID)
- パスキー(Passkeys)
- なぜ有効なのか:
- FIDO2/Passkeyによる認証は、利用者が「秘密鍵(デバイス内にある情報)」を持っていることと、アクセス先の「ドメイン(Webサイトのアドレス)」を暗号技術で紐付けて検証します。仮に被害者が偽サイト(例:
login.micros0ft.com)にアクセスしても、デバイスに保存された秘密鍵は「正規のドメイン(login.microsoft.com)以外には応答しない」ように設計されています。 利用者が騙されても、認証情報が偽サイトに送られること自体がないため、攻撃者はMFAを中継(横取り)することが原理的に不可能です。SMSや認証アプリが「知っている情報(コード)」を検証するのに対し、FIDO2は「信頼できる場所(ドメイン)で、信頼できるモノ(キー)が使われているか」を検証します。これが「フィッシング耐性」の本質です。
- FIDO2/Passkeyによる認証は、利用者が「秘密鍵(デバイス内にある情報)」を持っていることと、アクセス先の「ドメイン(Webサイトのアドレス)」を暗号技術で紐付けて検証します。仮に被害者が偽サイト(例:
CISA*はphishing-resistant MFAとして最優先採用を推奨。
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/fact-sheet-implementing-phishing-resistant-mfa-508c.pdf
*CISA(米国サイバーセキュリティー・インフラセキュリティー庁)
ゼロトラスト・アーキテクチャの導入と条件付きアクセス
「一度認証したら信頼する」という従来の境界型防御(ペリメータ・モデル)を捨て、「常に検証する」ゼロトラストの考え方を導入します。
特にMicrosoft 365やGoogle Workspaceでは「条件付きアクセス(Conditional Access)」ポリシーの強化が有効です。
- 具体例:
- 会社の管理下にあるデバイス(MDM登録済み)以外からのアクセスを原則ブロックする。
- 日本国外や、通常業務ではあり得ないIPアドレスからのMFA成功を異常とみなし、追加認証を要求、またはブロックする。
- セッションの有効期間を短縮し、リスクが検知された場合は即座にセッションを無効化する。
攻撃者が認証に成功しても、その後の「振る舞い」が通常と異なる(例:海外のIPアドレス、管理されていない端末)場合、アクセスを遮断することが可能になります。
URLフィルタリングおよびDNSセキュリティの強化
攻撃の入口であるフィッシングサイトへのアクセスを、技術的にブロックする施策も重要です。
- 既知の悪性ドメインや、新規に登録されたばかりのドメイン(NRD: Newly Registered Domains)へのアクセスを、ネットワークレベルで遮断するセキュリティ製品(セキュアWebゲートウェイやDNSフィルタリング)を導入します。
EDR(Endpoint Detection and Response)による監視
万が一、従業員の端末(エンドポイント)が侵害された場合に備え、EDRソリューションを導入します。 EDRは、端末上での不審なプロセス(例:ブラウザからの異常な通信、セッション情報の窃取を試みる動作)を検知し、管理者に警告、または自動的に隔離することができます。
高度なフィッシングシミュレーション訓練
従業員教育も、従来の「リンクをクリックしない」レベルからアップデートが必要です。 「MFAを要求されたが、心当たりがない」「ログイン通知が来たが、自分ではない」といった、攻撃の「兆候」を検知した際に、即座にIT部門へ報告(エスカレーション)するプロセスを徹底的に訓練します。
まとめ:MFAへの「過信」を捨て、次世代の防御へ

リアルタイムフィッシングは、私たちが「安全策」として依存してきたSMS認証や認証アプリという前提を崩壊させる、非常に強力な攻撃です。
「MFAを導入しているから安全」という認識は、もはや過去のものです。 この巧妙な攻撃に対抗するためには、攻撃者が介在する余地のない「FIDO2/Passkey」といったフィッシング耐性MFAへの移行が、今や必須の経営課題となっています。
自社の認証基盤を見直し、ゼロトラストの原則に基づいた多層的な防御を構築すること。それこそが、巧妙化するサイバー攻撃から企業の重要なデジタル資産を守る、唯一確実な道筋です。